 (図1)
(図1) 『写真時代/S.60.1月号』に荒木経惟の連載写真『景色/ピッカビア・ダダイズ無』が載っている。その写真はいくつもの指に押し広げられた女陰にブルーのポスターカラーがドリッピングされている。そして「芸術はオマンコにつける薬だ。フランシス・ピッカビア」(図1)
と解説されているのだ。
ここでは、単に女性性器の拡大写真にすぎないものが、多分男たちの指と思われるものによって押し広げられることによってスケベ的価値を担った<オマンコ>となり、さらにその上にポスターカラーという<薬>をつけることによって、その写真は<ダダイズム>の芸術否定論を逆手に取りながら「薬のついたオマンコは芸術だ!!」というわけで、芸術への否定的行為を仕掛けながら芸術的経験を正当化するという見事なほどの<芸術作品>となっているのだ。たとえそれが、ピッカビアによる芸術批判の歪曲であるにしても、批判された芸術を肯定的に取り上げることもまた正当的な芸術的行為たりうるというわけなのだ。
 (図1)
(図1)
そこで、あの釈尊でさえ悟りを得る冥想において散々スケベに悩まされたことを見定めつつ、あらゆる自己認識から<スケベ>を払拭しえぬと悟るわれわれは、<何>論的自己認識を目指して「スケベをスケベする」ために、<スケベ的自己認識>に並々ならぬ情熱を持つ表現者として荒木経惟を取りあげることにより、この荒木的<スケベ芸術論>を<スケベ>しようという算段なのだ。ここで、かねがね「芸術家とはソープ嬢という芸術にたかるヒモだ」と主張しつづけてきたわれわれとしては、何はともあれ芸術が<オマンコ>につける<薬>にすぎないことに大いに賛同するわけであるから、この芸術を<何>化するために「スケベをスケベする」手法を駆使しようとするならば、それはとりあえず<芸術作品>として提示されているものから<薬>という芸術のエッセンスを取り除くという作業になるはずなのだ。
まず、この<オマンコ芸術>なるものからポスターカラーという<薬>を摘出してみると (図2) 、その摘出された<薬>は自らの霊力によって女性性器を芸術へと昇華させる台座としての悍しき欲望を喪失しているために、もはや十全たる芸術のエッセンスとは言えないものに成り下がっていることになる。そして一方の<オマンコ>も、<薬>という芸術のエッセンスを摘出
(図3) されてしまえばやはり芸術たりえず、しかもポスターカラーに隠されてこそ<オマンコ>たりえた女陰は、<隠すという欲望>を去勢されることによってすでに<オマンコ>たりえないのみならず、ほとんどを切り抜かれた写真はもはや満足な女陰写真でさえなくなっているのだ。
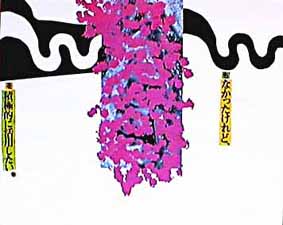

(図2) (図3)
つまり、荒木によるポスターカラーのドリッピングを<スケベする>ことは、<スケベ芸術論>を芸術たりえないもとしつつ、しかも<スケベ>とさえ言えない<何か>を提示することになり、正に<スケベ芸術>における<何>的反省は、見事なほどに「<スケベ的欲望>と<芸術的欲望>と<表現の自由を管理する欲望(卑猥な国家権力)>」を<宙づり>にしえたことになるのだ。
そもそも芸術的野心とは、下心のあるオジサンたちが初心な少女を手込めにせんと「一度スケベされてしまえば後は<何>も恥ずかしいことはないよ」と言い寄るようなものだと見定めるならば、<何>論は「どんなスケベもスケベされてしまえば<何>もいやらしいことはない」と言うようなものだから、純真無垢な欲望をわざわざ汚して清浄観を悟らせるというわけで、かなりきわどい欲望の戯れというわけなのだ。
言い換えるならば《スケベの宙づり》とは、「宙づりにする欲望」にとっては「<何>するスケベ」でありつつ「スケベする<何>」ということになり、「宙づりにされる欲望」にとっては「<何>されるスケベ」でありつつ「スケベされる<何>」でありつづけるということなのだ。もはや<何>論の前においては、<スケベ>もうかつに<スケベ>してはいられない事態になったのだ。
格助詞<の>について『新明解国語辞典』を引くと「(1)あとにくる言葉の内容や状態・性質などについて限定を加えることを表わす。(2)あとにくる動作・状態の主体であることを表わす。(3)上の語を体言として扱うことを表わす。(4)理由・根拠・主体の立場などを説得的に述べることを表わす。(5)あれこれ列挙して述べることを表わす」となっている。ここで格助詞<の>の役割を考えるために、上記の五つの役割にそれぞれの場面を想定し、そこで<の>を削除するとどうなるかを見てみたいと思う。
(1)「私<の>おんな」から<の>を削除すると、こういう勝手な言いかたのできる思い上がった男が、ある日女の怨念に憑り付かれ思わず女に変身してしまう怪奇物語に迷い込んでしまったり、あるいは突如倒錯的な快感に目覚めてしまったことになるし、「君<の>ため」から<の>を削除すると、君は誰かの大きなお世話から解き放されるかもしれないが、同時に誰かからの善意を失いかねないことになるし、「行者<の>ようだ」から<の>を削除すると、目が吊り上がり神懸かった誰かの風貌が、「これは行者用だ!」となって行者の持ち物になったり、行者さんに何か用事があるのかと間違ってしまいかねないのだ。
(2)「あなた<の>帰りを待ちます」から<の>を削除すると、「あなた<が>帰りを待ちます」という意味と区別が付かなくなってしまうから、<私>が待つのか<あなた>が待つのか分からなくなってしまうのだ。
(3)「この犬は君<の>だ」から<の>を削除すると、いつの間にか君は犬に変身して鎖に繋がれた生活へと転落してしまうのだ。
(4)「君はあしたも来る<の>か?」から<の>を削除すると、「もう来なくてもいいよ」という<私>のうんざりした気分が欠落して、まるで君が来ることを期待しているかのようにさえ誤解されてしまうのだ。
(5)「ひでえ<の>ひどくねえ<の>って、お話しになりゃしない」から<の>を削除すると、お話しにもならない惨たんたる有り様が、あなたの強引なやり方が<ひどい>とか<ひどくない>とか色々難癖を付けられて苦労した話しになってしまうのだ。
こんな訳で、<の>ひとつを削除しただけで文の意味はまるで変わってしまいかねないのだから、とりあえず格助詞<の>の機能については、前後の言葉を繋ぐことによって固有の意味・価値を語り起こすことと言える。そこでいまわれわれが、格助詞<の>について注目するところは、<の>が言葉の接着剤として表現者の欲望を刺激してやまないということについてなのだ。つまり、格助詞たる<の>は表現欲望の連鎖反応を触発するというわけなのだ。
たとえば、「5月<の>ようやく桜<の>盛りが終わる頃<の>新緑<の>芽吹き<の>まぶしい高原<の>さわやかな風<の>輝き<の>中<の>いまだ何とも語られていないもの<の>囁きが、ことごとく<の>私的なる欲望<の>亡霊に憑きまとわれた者<の>私たりえぬ私<の>真っ只中を突き抜ける耳鳴り<の>とめどなく昇りつづける衝撃音<の>永劫に辿り着けぬと諦めた沈黙<の>虚空をかすめて、とりあえず<の>私<の>いまだ語られていない反省<の>希望に桜<の>花びらを投げ掛けるけれど…」というわけで、<の>は、いつでもヒトビトの表現欲求を刺激して絵実物的欲望を担う言葉のブロックを積み重ね、壮麗なる欲望の殿堂である不滅の伽藍を夢見ているのだ。
しかしわれわれは、<空言><戯言>によってこそ言葉に託された自愛的欲望を解消しようというわけであるから、ここではこの格助詞たる<の>の「語り続ける情熱」こそを引き受けて、とめどない<何>的反省のために「何の何の何の何の何の何の何の何の何の…」というように、自らの情熱によって語るに落ちる「実りのない表現」の連鎖反応を喚起していきたいと思うのだ。
それにしても欲望連鎖を喚起しつづける格助詞たる<の>は、正に<スケベ>という戦略で欲情界に君臨する生命原理のようなものだから、それは表現世界における<性器>そのものの姿といえる。われわれは、そんな<の>を「荒木的スケベ芸術」の<女陰>のごとく拡大してみようというわけであるが、そこに絵実物的な<OMANKO>を見るのかあるいは<何>化すべき表現者の「荒れるにまかせる欲望」を見るのかは、表現者が何によって<私たりうる私>を確保しているのかという<自己愛>の在り方にのみ任されているのだ。
そこで、思わず<の>で欲情してしまう表現者を反省者へと誘う「行くあてのない<の>」あるいは「<何>論的<の>」の企みとは、たとえば<季節外れのトマト>あるいは「行くあてのない<味覚>」を語ることでもあるのだ。
いま<季節外れのトマト>とはおおかた<温室トマト>ということになっているようであるが、この<温室トマト>はその出生がすでに構造的に資本主義経済という人間的な「荒ぶる自然=欲望」の産物であり、しかも「味気無さ」によって<味覚>という<価値=暴力>を満足しえぬ発育不全であるために、温室というビニール・パッケージによって捏造された<味覚>と掠奪された<季節感>を担いつつ、同時に掠奪された<味覚>と捏造された<季節感>でもあるという自己矛盾を露呈するのだ。
それと同様に格助詞たる<の>は、関連のない言葉を繋ぐことにより新たなる<意味・価値>を捏造し言葉の絵実物的創造のために表現者の<表現欲望>を掠奪して、同時に<の>は言葉の霊力を高めて表現者を奮い立たせて<表現欲望>を捏造しつつ、言葉が本来担っていた<意味・価値>を表現者の絵実物的欲望によって掠奪してきたのだ。
そんなビニール・パッケージ的構造を担う<の>が、<何>的反省を喚起するだけの<の>として、<温室トマト>と同様に自らの存在理由をビニール・パッケージしてしまえば、<の>は行くあてのない<欲望>と<意味・価値>の狭間で、<何も>掠奪しないにもかかわらず<何>を掠奪して<何か>を捏造し、<何か>を掠奪しつつ<何も>捏造することがないにもかかわらず<何>を捏造するという「何って何!?」のために、黙っていても表現者として生きつづけてしまうヒトビトの「荒ぶる自然」ゆえの<欲望>と<意味・価値>を、人間的であることの「積極的な不自然」へと<掠奪=捏造>しつつ、同時に人間的であることの「消極的な自然」を<捏造=掠奪>しつづける「戯れの自然」になっているのだ。